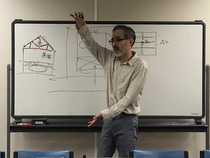勉強会
勉強会 · 13日 3月 2025
昨日は和のトラスと伝統を学ぶ会の勉強会の日 二次元の斜材の話から 三次元斜材である隅木 三次元トラスの隅合掌 三次元の加工を可能とした 道具 さしがね の話をしました
勉強会 · 02日 9月 2022
現在建て方進行中の 愛農学園農業高等学校 食農棟 の構造体の見学会を 和のトラスと伝統を学ぶ会 を共に開催する (株)木匠さんが企画して下さいました。 今日のある方はチラシの連絡先にお願いします。
勉強会 · 22日 7月 2022
7月のテーマは「トラスの仲間斜材の話」 伝統木造ではあまり活用してこなかった斜材について 知らなかったから使わなかったんじゃなくて、 知ってたけど使わなかった意味と 斜材の本来の使い方について お話しました。
勉強会 · 19日 5月 2022
「伝統木造の継手の原理」 このテーマは最初に勉強会を始めた時から 毎回繰り返し喋ってきた話。 挿絵が増え、 模型が増えたけど、 言いたい事は変わらない。 木は生きた材料である。 繊維である。力の向きがある。 繊維を利用した継手をつくる。
勉強会 · 13日 4月 2022
トラスは梁間の大きな建物に使う技術 という意識を離れて、 強くて、長く使える 使い勝手の自由がある 規格建物 という設計をする為の 一つの手法の技術として どんな事が出来るのか? を話しました。

木造トラス研究所・(株)合掌
〒630-8115 奈良市三条栄町15-13-3
〒630-8127 奈良市三条添川町3-12-1
Tel: Fax(0742) 36-2929